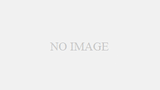「また通販でよくわからない商品を買っていた…」
「解約できない定期購入を知らぬ間に契約していた…」
高齢者の通販利用に悩むご家族は、年々増えています。
一度ハマると止めるのが難しく、なかには悪質な業者や詐欺的な定期購入トラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
特に一人暮らしや認知症を抱える高齢者の場合、本人には「悪気がない」ため、やめさせ方に苦慮するご家族も多いのが現実です。
この記事では、
- 高齢者が通販をやめられない背景と心理
- 典型的な通販トラブルのパターン
- 家族が実践できる安全な対策
- 成年後見制度やクーリングオフなどの法的手段
- 国民生活センターなど相談窓口の活用法
をわかりやすく解説します。
感情論ではなく、現実的かつ効果的に通販をやめさせるための具体策を知りたい方に向けた内容です。
高齢者が通販をやめられない理由
高齢者が通販にハマる心理
高齢者が通販をやめられない背景には、心理的な要因が大きく関係しています。特に「テレビやカタログを見ながら商品を選ぶこと」が日常の楽しみになっているケースが多いのです。年齢を重ねると外出の機会が減り、買い物の楽しみが自宅で完結する通販に移行しやすくなります。
また、通販は電話一本で簡単に注文できるため、「気軽さ」が依存を強める要因になります。さらに、届いた商品を手にすることで満足感や安心感が得られやすく、それが繰り返しの購入行動につながってしまいます。本人にとっては「楽しい買い物」の一部であり、「悪いことをしている」という認識が薄いことも特徴です。
一人暮らしと孤独感の影響
一人暮らしの高齢者は、孤独感や不安感を紛らわせるために通販に依存しやすくなります。誰かと会話をする機会が少ない生活の中で、電話オペレーターとのやり取りや、商品が届くこと自体が「社会とのつながり」と感じられる場合もあります。
特にテレビ通販などは温かい語り口で商品を紹介するため、「自分の味方」や「親近感」を感じやすく、心理的な距離感が近くなる傾向があります。孤独を埋める手段としての通販依存は、単なる買い物習慣ではなく、心理的なケアが必要な問題でもあります。
認知症・判断力の低下による衝動買い
認知症や軽度の認知機能低下がある高齢者は、判断力が落ちているために衝動的な購入を繰り返してしまうことがあります。広告の言葉をそのまま信じてしまったり、定期購入や高額な契約の内容を正確に理解できないまま申込んでしまうケースも少なくありません。
また、認知症の場合は同じ商品を何度も注文する「重複購入」が起こることも多く、家族が気づいたときにはかなりの金額になっているケースもあります。こうした状況は本人の意思では止めにくく、周囲のサポートが不可欠です。
定期購入やテレビ通販の仕組み
通販の中でも特に問題になりやすいのが、「定期購入」の仕組みです。初回限定価格で安く見せかけ、実際には複数回の購入が前提となっているケースが多く、契約の途中で解約しにくい構造になっている場合があります。
テレビ通販の場合、華やかな演出とわかりやすい説明によって、商品が「とてもお得」に見えるよう巧妙に設計されています。高齢者はこうした演出を信じやすく、衝動的に電話をかけてしまうケースが後を絶ちません。通販の仕組みそのものが、高齢者の心理を突いたビジネスモデルになっているのです。
よくある通販トラブルと危険なケース
定期購入・解約できないトラブル
最も多いトラブルのひとつが、「定期購入の解約ができない」という相談です。初回は数百円や1,000円程度でも、2回目以降は高額な商品代金が請求され、契約期間内は解約ができないようになっているケースもあります。高齢者本人は契約内容を理解していないことが多く、「安いと思って買ったのに、請求が止まらない」という状況に陥りがちです。
高額商品や健康食品の勧誘
もうひとつ多いのが、健康食品や高額なマッサージ機器、美容器具などの強引な勧誘です。「今ならお得」「健康にいい」といったセールストークに弱く、実際には必要のない商品を何十万円も購入してしまうケースもあります。特にテレビや電話での勧誘は断りにくく、気づかぬうちに契約が成立してしまうこともあります。
悪質な訪問販売・詐欺の手口
通販と混同しやすいのが、訪問販売型の詐欺です。電話で注文を装い、実際には高額商品を押し売りするケースもあります。悪質な業者は高齢者が判断力に不安を抱えていることを利用し、強引に契約を迫るため、本人が断れないままサインしてしまうケースも少なくありません。
家族が気づきにくいサイン
高齢者の通販トラブルは、家族が気づきにくいという点も大きな問題です。特に一人暮らしの場合、通販で届いた商品や請求書が家の中に溜まっていても、家族が見る機会がありません。
また、本人は「必要だから買っている」と思い込んでいるため、問題を表面化させないこともあります。家族が「最近荷物が多い」「カードの請求額が増えた」といったサインを早期に察知することが、被害を防ぐカギとなります。
高齢者の通販利用をやめさせる実践的な方法
家族ができる声かけとサポート
高齢者の通販利用を止めるうえで、まず大切なのは「頭ごなしに叱らない」ことです。通販を利用している背景には、孤独感・楽しみ・健康不安といった心理的な要因があるため、頭ごなしに「やめなさい」と言うと反発され、逆に隠れて購入するようになるケースもあります。
そのため、まずは「なぜ通販を使っているのか」を一緒に聞き取り、安心感を与えることが第一歩です。例えば「必要なものがあるなら一緒に探そう」「安全な方法を一緒に考えよう」という前向きな声かけが効果的です。
また、家族が一緒に通販サイトを確認したり、購入履歴を見守ることで「自分は見守られている」という安心感が高齢者の行動を自然と抑制するきっかけになります。心理的な信頼関係を築くことが、行動を変える最も有効な手段です。
支払い方法の制限・見直し
高齢者の通販トラブルでは、クレジットカードや口座引き落としによる「定期購入」や「高額請求」がよく見られます。そのため、支払い手段をあらかじめ制限しておくことが実践的な対策となります。
具体的には、クレジットカードの利用上限を引き下げる、不要なカードを解約する、代引き・コンビニ払いのみに絞る、といった方法が有効です。これにより、本人が衝動的に購入しても高額な契約に至るリスクを抑えられます。
さらに、家族のアカウントに紐づけて決済状況をチェックできるようにすることで、問題が起きた際にすぐ対応できる体制を作ることも重要です。支払いの流れを「仕組み」で制御することが、トラブル予防の近道です。
通販サイト・アプリのブロック設定
高齢者の通販利用をやめさせたい場合、通販サイト自体へのアクセス制限も非常に有効です。スマートフォンやパソコンのブラウザ設定で通販サイトのURLをブロックしたり、フィルタリング機能を活用すれば、衝動的な購入を防げます。
特にスマホのワンタップ注文やテレビショッピング経由での申込みは、簡単すぎるがゆえにトラブルの原因になりやすいポイントです。アプリをアンインストールしたり、家族の同意なしに注文できないよう設定しておくことで、行動を未然に防ぐことができます。
また、操作に不慣れな高齢者はブロック設定を自分で解除できないことが多いため、物理的な制限として非常に効果的です。
クーリングオフや契約解除の手順
すでに通販で契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度を活用すれば解約できるケースがあります。特に定期購入や健康食品の契約では、契約書面の受け取りから8日以内であれば無条件で解約可能です。
高齢者本人が対応できない場合でも、家族が代理で手続きを進めることができます。クーリングオフの書面を送る、メールで申請する、消費生活センターに相談するなど、具体的な流れを早めに行動することが大切です。
また、悪質な業者の場合はクーリングオフ期間を過ぎても「不当な勧誘」や「意思能力の欠如」によって契約の無効を主張できる場合もあります。諦めず、まずは相談機関に連絡するのが鉄則です。
認知症の場合に必要な対応と制度
判断能力の低下と購買行動
認知症を抱える高齢者の通販トラブルは、本人に悪意がなくても深刻化しやすい傾向があります。判断能力が低下しているため、商品の必要性や契約内容を理解できずに購入を繰り返すケースが多いのです。
また、認知症の方は「前に買ったことを忘れて同じ商品を注文する」「セールスの話を鵜呑みにしてしまう」といった行動をとることがあります。この段階では「説得」だけでやめさせるのは難しく、仕組み的な制限や制度の活用が不可欠です。
成年後見制度の活用
判断能力が十分でない場合、成年後見制度の利用を検討することが有効です。成年後見制度を活用すると、家族や後見人が契約行為を代理・取消しできるようになり、不必要な通販契約を防ぐことが可能になります。
家庭裁判所を通じて手続きを行い、後見人が選任されると、契約を事前に制限したり、悪質業者との取引を無効にできるケースもあります。特に認知症が進行している場合は、本人の意思よりも「生活を守ること」を優先する視点が必要です。
代理人・家族ができる契約解除手続き
認知症の場合、本人が解約手続きを行うのは困難です。そこで、家族や代理人が積極的に関与する必要があります。業者に連絡し、代理での契約解除が可能かを確認する、または成年後見人として契約無効を申し立てるなど、法的なルートを活用します。
この際、購入履歴や請求書、通話記録、契約書などの証拠を整理しておくと、スムーズに解約を進めやすくなります。時間が経つほど対応が難しくなるため、できるだけ早期に動くことが重要です。
地域包括支援センターの活用
通販トラブルへの対応は家族だけで抱え込む必要はありません。各自治体にある地域包括支援センターでは、高齢者の消費トラブルに関する相談が可能です。介護支援専門員(ケアマネジャー)や社会福祉士が連携し、成年後見制度の利用や消費生活センターとの橋渡しを行ってくれます。
また、認知症の進行度に応じたサポートプランを立て、通販行動を制限する環境づくりを支援してもらえるケースもあります。公的な支援を活用することで、家族の負担を大きく軽減しながら、根本的な対策につなげることができます。
相談できる窓口と支援先
国民生活センターの相談方法
高齢者の通販トラブルに対応する代表的な相談先のひとつが「国民生活センター」です。
通販業者とのトラブルが発生した際、本人や家族が直接相談することで、クーリングオフ制度の適用や業者への交渉支援を受けられる場合があります。
特に「定期購入をやめたい」「解約できない」「高額な請求が届いた」といったケースでは、早めの相談が非常に効果的です。
国民生活センターは電話(188番)での相談が可能で、トラブル内容を聞き取り、適切な窓口への案内や法的アドバイスを行ってくれます。
専門の相談員が対応するため、通販に慣れていない高齢者や家族でも安心して利用できます。
消費生活センターの活用
通販トラブルが地域の問題として発生した場合は、各自治体にある「消費生活センター」を利用するのも有効です。
国民生活センターと連携しており、より地域に密着したサポートが受けられるのが特徴です。
業者とのやりとりに同行してくれたり、法的手続きに必要な情報を提供してくれるケースもあります。
特に認知症を抱える高齢者や一人暮らしの親を持つ家族にとって、こうした「第三者の介入」は非常に心強い存在です。自力で解約や交渉が難しい場合には、まず地域の消費生活センターに連絡を入れるのが良いでしょう。
警察・自治体・弁護士への相談
もし通販トラブルが悪質な詐欺や違法な契約の可能性がある場合は、警察や弁護士への相談が必要になることもあります。
詐欺まがいの業者は巧妙に法の抜け道を突いてくるため、家族だけで対処するのは限界があります。警察には「消費者被害の相談」として届け出ることが可能で、被害が拡大する前に介入してもらえる場合もあります。
また、弁護士に相談することで、クーリングオフ期間が過ぎた場合でも契約の無効や損害賠償請求など、法的な手段を取ることも可能です。自治体の無料法律相談を利用すれば、費用を抑えながら専門家の助言を得られます。
相談時に準備しておくべき情報
相談をスムーズに進めるためには、トラブルの記録を整理しておくことが非常に重要です。
以下の情報を事前にまとめておくと、相談先が的確な対応を取りやすくなります。
- 購入した商品の明細や領収書
- 契約書・申込書・メール・チャット履歴
- 請求書やクレジットカード明細
- 通話記録(電話注文の場合)
- 本人の状態(認知症の有無や判断力の状況など)
これらを準備することで、相談員や弁護士が事実関係を迅速に把握でき、効果的な対応策が提示されやすくなります。特に高齢者のトラブルは時間との勝負になることが多いため、早い段階での情報整理がカギになります。
よくある質問(FAQ)
高齢者の通販トラブルはどこに相談すればいい?
まずは「188」に電話して国民生活センターへ相談するのがおすすめです。トラブル内容によって、消費生活センターや警察、弁護士への連携もスムーズに行えます。
勝手に通販契約してしまった場合の対処法は?
クーリングオフ制度を活用することで、多くのケースは解約が可能です。契約書の受け取りから8日以内であれば無条件で解約できます。期限を過ぎていても悪質業者の場合は無効主張ができる可能性があります。
家族が代わりに解約できる?
はい。認知症などで本人が対応できない場合、家族や代理人が代わりに解約手続きを進めることが可能です。クレジットカード会社に連絡する、業者へ代理交渉を申し出るといった方法が取れます。
認知症でも通販契約は有効?
原則として有効とされますが、意思能力が欠けていたと判断されれば無効になる可能性があります。そのため、早期に成年後見制度の活用や法的手段を検討することが重要です。
予防するためにできることは?
支払い方法の制限、通販サイトやアプリのブロック設定、家族による購入履歴のチェックなど、物理的な制限と心理的なサポートを組み合わせることが効果的です。さらに、自治体の支援機関と連携することで、トラブルの芽を早い段階で摘むことができます。